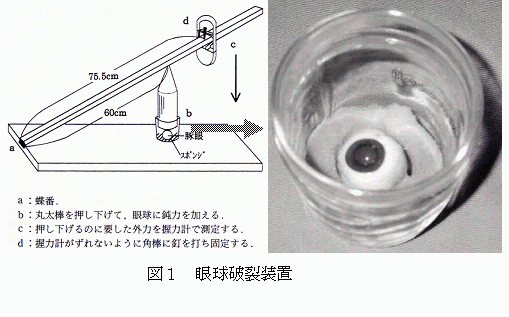
2.材料強度学とは 「安心・安全」な社会を構築することは,現代社会において極めて重要なことである.機械工学の分野では,破壊事故を起こさないことが最も重要な課題であるが,現実には事故が後を絶たない.材料の強度を正確に把握し,破壊を予測する学問が材料強度学である.材料強度学を英文で表すと ”Strength and fracture of materials” であり,内容を良く反映している.材料強度学は単に強度を対象とするのではなく,「破壊」が重要な研究対象である.工学における「材料」は機械や構造物などの物であり,医学では人である.
機械工学における材料強度学の重要な役割は「寿命予測」である.すなわち,機械構造物が壊れることなく使用できる期間を正確に予測し,必要に応じて検査や補修を繰り返しながら,破壊事故を起こすことなく機械構造物全体としての寿命に至るまで,その機能を使い切ることである.検査や補修の対象となるのは,機械構造物を構成する部品であり,個々の寿命予測に基づいて検査や補修の間隔が決められる.一方,全体の寿命は,部品の交換や補修費用が頻繁に発生したり,技術革新によって時代遅れとなったりして,機械構造物全体を新しいものに取り替えたほうが経済的に有利になったときに,経済寿命と呼ばれる観点から決定される.
医学における寿命予測は全く異なる意味を持っていると思われるが,「人間の絶対寿命は120歳」という話を聞いたことがある.どんなに健康な人も120歳以上は生きられないらしい.機械構造物の絶対寿命は存在しない.適切な点検・維持管理を行えば,経済寿命に至らない限り使い続けることができる.例えば,1970年代に建設された初期の原子力発電所は,想定寿命を40年として建設されたが,最新の材料強度学的な知識を利用して,現在のところ60年まで使い続けることになっている.20年後には更なる寿命の延長が行われるのではないかと思われる.
3.骨疲労と金属疲労 両者に共通する破壊の問題として「疲労」があげられる.スポーツ選手が厳し過ぎる練習により骨疲労を起こして骨折することがしばしば報道されている.一方,金属疲労は1985年の日航ジャンボ機墜落事故を契機に,日本国内で広く知られるようになった.空気の薄い成層圏を飛行するジェット旅客機は,上空で客室内の気圧を一定に保つようになっていて,機体は飛行のたびに内圧を受けた状態となる.この時,機体には引張力が作用する.この現象が繰返されると疲労き裂が発生し,さらに徐々に成長して大きくなり,機体が破裂することになる.もちろん,き裂が発生しないように頑丈な機体を作ることは可能であるが,重い機体では空を飛べない.すなわち,航空機は適切なメンテナンスを行わない限り安全に使用することはできない.空港の周辺に見られる巨大な格納庫の中では,安全の鍵を握る航空機の整備が行われている.航空機はき裂ができることを前提にして維持管理されている.き裂がある部材でも,材料強度学の一分野である破壊力学という学問を使えば,安全に使用することができる.
骨疲労が発生しても,固定して安静にしていれば自然に治る.しかも,損傷が発生すれば痛みという形で検知する機能がある.機械工学で用いる材料は絶対に自然治癒することはないし,特別な工夫をしない限り損傷の検知はできない.これらの意味で,生体材料は極めて優れた材料である.機械工学では,生体材料をお手本にしたスマートマテリアルという研究分野があるが,構造材料として本格的に用いる段階にはない.
4.眼球の強度 筆者は眼球強度を調べる研究に関与した経験がある.この研究では,近視手術である放射状角膜前面切開術を施した場合,どの程度眼球の破裂強度が下がるのか,またどのような切開方法の破裂強度低下が小さいかを調べることを目的とした(1).実際には,食肉加工場から調達した豚の目に手術を施し,それを圧縮破壊させて破裂強度を測定するものである.強度評価の基本的な考え方は機械工学で用いられる材料試験方法と同じであるが,生体が対象であることから試料の保存ができない点が大きく異なる.
本研究は筆者の知人の眼科医から相談を受けたものであり,病院で実験を行うことが想定された.したがって,機械工学で用いるような試験装置を使うことはできない.そこで,図1に示すような簡単な器具を作製して実験を行った.破裂に要する力を測定するために,握力計を使っている.もちろん精度の高い実験を行うことはできないが,本研究の目的である破裂強度の相対的な比較を行うには十分である.これにより,手術直後に眼球の破裂強度を測定できた.
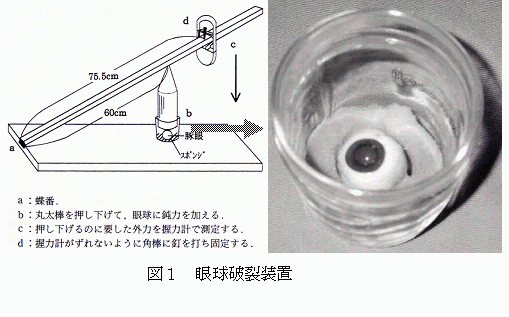
5.微小材料の強度評価 最近のヒット商品は,おしなべて小さい.特に,携帯する電気製品は信じられないぐらい小さくなった.携帯音楽プレーヤー,携帯電話,PDAなどである.これらの電子機器は,一見機械工学と関わり合いがあるとは思えないが,壊れないように作るために機械工学が重要な役割を持っている.携帯機器の中には集積回路があり,多くの部品がはんだ接合されている.無数にある接合部の一つでも壊れて断線すれば,機器全体の機能が失われたり,誤動作を起こしたりすることになる.機械工学では,材料の強さを正確に測定することによって破壊しない設計を行う.しかし,一般的に材料の強さは寸法に依存することが多く,従来の機械工学で用いてきた手法は,微小な材料にそのまま使うことができない.
この問題に関して筆者が力を入れて研究しているのは,図2に示すインデンテーション法である.この方法は鋭利な先端のダイアモンドを材料に押しつけて試験を行うものである.図2には微細なはんだ接合部の評価を行った例を示している.機械工学における微小材料の評価方法は,医学への応用が期待されている.例えば,評価手法は異なるが,MITのSuresh教授は材料科学的な方法で血液細胞の力学特性を評価し,マラリア患者の血液細胞は健康な人より硬くて脆いことを明らかにしている(2).
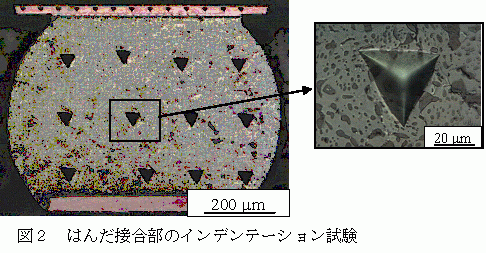
6.リスクベース工学 機械工学では,「リスクベース」の設計・維持管理・検査などの方法が積極的に導入されつつある.図3は日本機械学会誌で小特集号が掲載された時の表紙であり,工学におけるリスクベースを表している(3).特に日本人は顕著であるが,人は物に対して絶対安全を求める.物とは原子力発電所,航空機,新幹線などである.しかし,自然災害が絶対に起きないということが不可能なように,物の絶対安全は神話でしかあり得ない.すなわち,危険と安全は二者択一ではなく,連続的な尺度によって評価されるべきである.この尺度が,事故発生頻度とその影響度により定義される「リスク」である.機械工学では,設計・検査・維持管理がリスクベースで行われるようになりつつある.
人が必ず死ぬことは当然のこととして受け入れられており,医学ではリスクの考え方は十分浸透しているのではないかと思われる.物は必ず壊れるのにそれは許されず,機械工学にリスクベースは,なかなか認められてこなかった.

7.おわりに 機械工学に携わっていると,冒頭で問題とした「人を物に例える」ことを,つい考えてしまう.臓器移植と部品交換,臓器提供と部品工場,出生前遺伝子診断と不良品検査,遺伝子治療と原子力開発などである.倫理的に極めて難しい問題ではあるが,新たな治療方法の可能性を探る上で,機械工学で行っていることが役に立つかもしれない.一方,機械工学は「人」だけでなく,多くの生命体にヒントを得ながら今後も発展してゆくと考えられる.
参考文献 (1) 放射状角膜前面切開術後の眼球強度(藤本可芳子,西村哲哉,小林誉典,小川武史),あたらしい眼科,メディカル葵出版,Vol.16, No.4, pp.541-547 (1999-4). (2) Connections between single-cell biomechanics and human disease states: gastrointestinal cancer and malaria (S. Suresh, J. Spatz, J.P. Mills, A. Micoulet, M. Dao, C.T. Lim, M. Beil and T. Seufferlein), Acta Biomaterialia, Vol. 1, Issue 1, pp. 15-30 (2005-1). (3) 日本機械学会誌表紙(峠レオ,小林英男,小川武史),Vol.106, No.1020 (2003-11).